1. 深夜の屋根裏部屋(ノイズの正体)
深夜2時。
『GRAVITY』の店舗部分は、古時計の針の音だけが支配する静寂に包まれていた。
けれど、急な階段を登りきった先にある屋根裏(ロフト)だけは、別の時間を刻んでいる。
「……チッ。またこれ。」

暗闇の中、無数のモニターが放つ青白い光だけが、その空間を照らし出している。
天井を走る太い木の梁と、床を這う無機質なLANケーブルの蛇。
幾重にも重なる冷却ファンの駆動音(ファン・ノイズ)が、低い唸り声のように響いていた。
その中心で、膝を抱えるように椅子に座っていたのは、黒崎 寧路(ネロ)。
彼女は苛立ちを隠そうともせず、自作のタブレット端末――『ステラ・ポータブル改』の基盤をいじっていた。
「……完璧なフィルタを組んだはず。理論上、外部干渉はゼロ。なのに、どうしてこの『ゴミ(ノイズ)』が消えないの?」
画面上の波形は、美しいサインカーブを描くはずの場所で、突発的に乱れ、ギザギザとした棘を作っていた。
彼女にとって、その正体不明の音は、自身の技術への冒涜であり、許しがたい汚れなのだろう。
2. リネアの訪問(二人の不協和音)
「……ネロさん。入ってもいいですか?」
私はトレーに夜食のサンドイッチとホットミルクを乗せ、声をかけた。
アイリス先生に「あの子は集中すると食事を忘れてしまうから」と頼まれたのだ。
「……今、忙しい。帰って」

ネロは振り返りもせず、冷たく言い放つ。
乱雑に積み上げられたサーバー機器と、飲みかけのエナジードリンクの缶。
ここは彼女の聖域(サンクチュアリ)であり、他者の侵入を拒む要塞だ。
けれど、私は足を踏み入れた。
なぜなら、彼女が睨みつけているそのスピーカーから、私には「別の音」が聴こえていたからだ。
『ザザッ……ガガッ……ピー……』
ネロにとっては、ただの不快な電子音。
でも、私の耳には違って聴こえる。
(これ……歌?)
矩形波(くけいは)の向こう側。
震えながら、何かを必死に伝えようとする、幼い少女のハミング。
それはノイズなんかじゃない。迷子のお知らせのような、切実な「孤独の周波数」だ。
「その音……ただの故障じゃないかもしれません」
「は? 非論理的(ナンセンス)。これはただの電波干渉。ハードウェアの接触不良か、プログラムのバグ。それ以外にない」
ネロが分厚い眼鏡の奥から、私を睨む。
その瞳は、モニターの光よりも冷たく、そしてどこか怯えているように見えた。
彼女もまた、世界との繋がり方がわからなくて、この電子の迷宮に引きこもっている。私と同じだ。
3. 調律(コードと旋律の交差)
「少しだけ、その子を聴かせてください」
私は彼女の拒絶を待たずに、作業机の横に膝をついた。
剥き出しの基盤。点滅するLED。
私は胸元のアンティークの鍵を強く握りしめ、その冷たいデバイスにそっと指先を触れさせた。
キィィィン……。
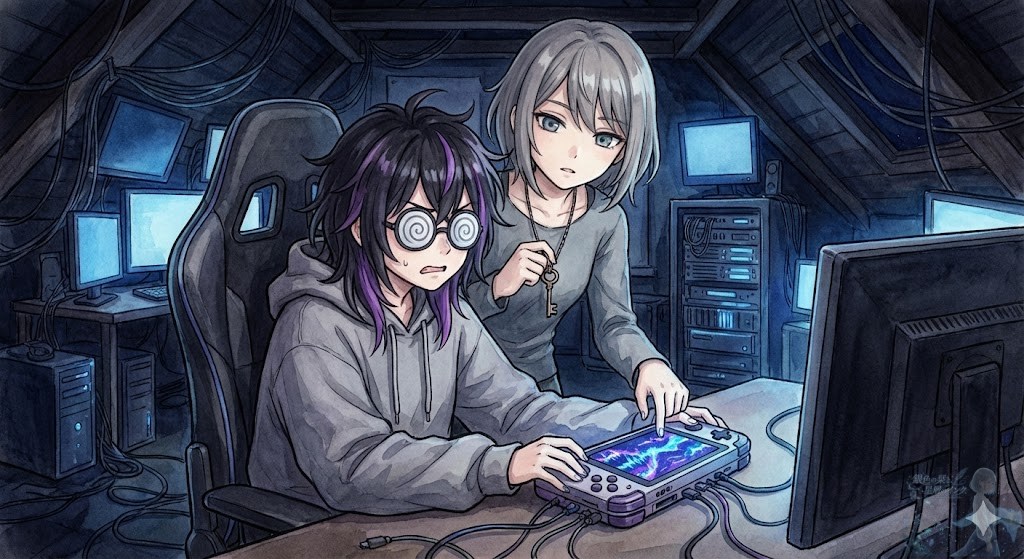
鍵が共鳴音を立てる。
耳の奥が熱くなる。デジタルの冷たい情報の羅列が、温かな「温度」を持った記憶へと変換されていく。
(合わせる。この子が泣いている理由に)
『ザザッ……』
不快なビープ音が、次第に減衰していく。
代わりに、スピーカーから流れ出したのは――。
――ポロン、ポロン。
古いピアノの音。
そして、雨が窓を叩く音。
『……こちらは、JOZZ。……誰か、聴こえていますか? 今夜も、雨が綺麗ですね』
「な……に、これ……」
ネロの手が止まる。
それは、かつてこの場所で――いいえ、この機械のパーツの一部に使われた古い部品が記憶していた、幻のラジオ放送。
誰にも届かなかったメッセージの残響。
「バグじゃありません。この子はただ、誰かに自分の声を聴いてほしかっただけ。ネロさんが、画面の向こう側の誰かを探しているのと同じように」
私がそう呟いて指を離すと、スピーカーからのピアノ音はフッと消え、モニターの波形は一本の美しい直線へと安定した。
4. 結びと次へのフラグ
屋根裏部屋に、ファンの音だけが戻ってきた。
ネロは信じられないものを見る目で、正常に動作し始めたタブレットと、私を交互に見比べている。
「……意味不明。オカルト。非科学的」
彼女はブツブツと呟きながら、眼鏡の位置を直した。
「でも……確かに波形が整った。ノイズ・キャンセリング完了。……悔しいけど、アンタの勝ち」

彼女は乱暴にサンドイッチを掴むと、バクリと齧り付いた。
それが彼女なりの、不器用な肯定だった。
「……ん。待って」
サンドイッチを飲み込むと、ネロの表情が技術者(エンジニア)のそれに変わる。
彼女はキーボードを叩き、今しがた消えた「ノイズ」のログを解析し始めた。
「この信号……ただの残留思念(メモリ)じゃないかも」
モニターに、栃木市の地図が表示される。
赤い点が、点滅していた。
「発信源は、この家(GRAVITY)じゃない。……ここ」
ネロの指が、地図の中心を指し示す。
「栃木市の中心にある『旧・ラジオ塔』。
……そこから、今も微弱な信号(SOS)が、定期的に発信され続けてる」
その言葉に、私は息を呑んだ。
過去の記憶だと思っていたものが、現在進行形の「誰かの声」だとしたら――?
(第5話へ続く)
